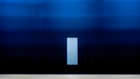ガドルフの百合

原作 宮沢賢治
演出. 振付. 照明. 美術. 衣装. 選曲 勅使川原三郎
アーティスティック コラボレーター 佐東利穂子
出演 勅使川原三郎、佐東利穂子
照明技術:清水裕樹(ハロ)
音響技術:三森哲弘(エスアールテックプランニング)
衣装製作:武田園子(ヴェロニク)
協力:宇佐美雅司、加藤智子
主催:有限会社カラス
企画制作:KARAS
特別提携:シアターX(カイ)
上演時間:60分
初演:2021年12月 両国・シアターX
演出. 振付. 照明. 美術. 衣装. 選曲 勅使川原三郎
アーティスティック コラボレーター 佐東利穂子
出演 勅使川原三郎、佐東利穂子
照明技術:清水裕樹(ハロ)
音響技術:三森哲弘(エスアールテックプランニング)
衣装製作:武田園子(ヴェロニク)
協力:宇佐美雅司、加藤智子
主催:有限会社カラス
企画制作:KARAS
特別提携:シアターX(カイ)
上演時間:60分
初演:2021年12月 両国・シアターX
「ガドルフの百合」 について
ガドルフは普通の旅人ではなく、放浪する男。
少年や若者と固定観念をふりはらい、読み考えてみれば、
彼は大人であり終わりのない、
終わりが見えない旅する男である。
人生の旅路に遭遇する嵐であり百合の花であり、
試練であり恋である。
解決が見えないただのがんばりである。挫けるな、
負けるなと心に叫びつづける歩みそのものである。
叫びはリズム、雷鳴は警告、
稲光りは驚きであり超絶的な運命の出会いである。
百合は白く、雷の稲妻と闘いついには勝つ、
力は美しい姿を立たせて暗闇から星を輝かせる。
放浪する男は自我の反映として百合に惹かれ、
その気持ちを恋というが、
彼の胸の中に育てた愛の嵐に出会った白い輝きとの再会でもある。
挫ける我が身の弱い心が見つけた勇気の姿である。
嵐が去り男は果てしない目的が不明な地に向かって歩を進める。
勅使川原三郎
ガドルフは普通の旅人ではなく、放浪する男。
少年や若者と固定観念をふりはらい、読み考えてみれば、
彼は大人であり終わりのない、
終わりが見えない旅する男である。
人生の旅路に遭遇する嵐であり百合の花であり、
試練であり恋である。
解決が見えないただのがんばりである。挫けるな、
負けるなと心に叫びつづける歩みそのものである。
叫びはリズム、雷鳴は警告、
稲光りは驚きであり超絶的な運命の出会いである。
百合は白く、雷の稲妻と闘いついには勝つ、
力は美しい姿を立たせて暗闇から星を輝かせる。
放浪する男は自我の反映として百合に惹かれ、
その気持ちを恋というが、
彼の胸の中に育てた愛の嵐に出会った白い輝きとの再会でもある。
挫ける我が身の弱い心が見つけた勇気の姿である。
嵐が去り男は果てしない目的が不明な地に向かって歩を進める。
勅使川原三郎
ギャラリー
レビュー(抜粋)
ダンスマガジン 2022年3月号
「舞踊という文芸批評」三浦雅士氏
「舞踊という文芸批評」三浦雅士氏
勅使川原三郎の十二月公演『ガドルフの百合』を見て強い衝撃を受けた。
素材となった宮沢賢治の『ガドルフの百合』の朗読(佐東利穂子)に配されるのは、ベートヴェンの弦楽四重奏、第十五番の第三楽章で、楽章冒頭に有名な「病より癒えたる者の神への聖なる感謝の歌」という言葉が付されたいわば曰く付きの旋律だが、さまざまな音、効果や前衛的な音楽が添えられていて、旋律そのものが全面に押し出されているという印象はまったく受けない。第三楽章そのものが、そこに付された言葉通り穏やかな旋律なのだが、その穏やかさが強調されている。上演を綿密に分析したわけではないので誤っているかもしれないが、第一主題の穏やかな旋律が、雷雨を思わせる効果音までをも包み込むように、ひっそりと無限に反復されているのである。
鮮烈なのはその後に、楽譜には「新しい力を得た」と付された第二主題が登場する場面で、物語の朗読が終わってどうなるのかと固唾を呑むその瞬間に初めて提示された第二主題とともに、すでに朗読されてしまった物語からさまざまな言葉が取り出され散乱反射してゆくその展開である。第一部に対する第二部という趣で、私の率直な印象ではここで物語が批評に転じるのだ。それもそれ自体が「詩」というほかない水晶のような言葉(たとえば「曖昧な犬」)が煌めいては消えてゆくというかたちで。
『ガドルフの百合』は、旅の途中に嵐に出会ったガドルフ(勅使川原)と白百合(佐東)とのいわば幻想的かつ一方的な恋愛譚だが、朗読が終わったその物語が新たに蘇って、思いもよらない解釈のもとに再展開してゆくことになる。まるで詩のかたちをした文芸批評。『ガドルフの百合』の深淵、賢治の深淵を覗き込む思いである。
私は、勅使川原が荻窪に開いた小劇場アパラタスでほとんど毎月のように新作を上演していることに驚嘆しているが、それはそのつどつねに新たな試みが展開されているからである。身体においてだけではない。
音楽、文学、美術、とりわけ照明すなはち影と空間の研究において凄い。舞台芸術の拡張。世界的に見て最先端を行くと言っていいその成果のすべてが、『ガドルフの百合』に流れ込んでいる。移った影が独自に動き始める。紗幕に映るはずのないものが映る。まるで魔術だ。とりわけ最後の「南の蠍の赤い光」、去って行くべきはずの赤いテールランプが高度を増し爆発して消えたのには呆然とした。勅使川原は照明をオブジェに変えたのである。
「言葉と影の繊細な研究」といっていいアパラタスの克明な上演記録が執筆されることを切に望む。
素材となった宮沢賢治の『ガドルフの百合』の朗読(佐東利穂子)に配されるのは、ベートヴェンの弦楽四重奏、第十五番の第三楽章で、楽章冒頭に有名な「病より癒えたる者の神への聖なる感謝の歌」という言葉が付されたいわば曰く付きの旋律だが、さまざまな音、効果や前衛的な音楽が添えられていて、旋律そのものが全面に押し出されているという印象はまったく受けない。第三楽章そのものが、そこに付された言葉通り穏やかな旋律なのだが、その穏やかさが強調されている。上演を綿密に分析したわけではないので誤っているかもしれないが、第一主題の穏やかな旋律が、雷雨を思わせる効果音までをも包み込むように、ひっそりと無限に反復されているのである。
鮮烈なのはその後に、楽譜には「新しい力を得た」と付された第二主題が登場する場面で、物語の朗読が終わってどうなるのかと固唾を呑むその瞬間に初めて提示された第二主題とともに、すでに朗読されてしまった物語からさまざまな言葉が取り出され散乱反射してゆくその展開である。第一部に対する第二部という趣で、私の率直な印象ではここで物語が批評に転じるのだ。それもそれ自体が「詩」というほかない水晶のような言葉(たとえば「曖昧な犬」)が煌めいては消えてゆくというかたちで。
『ガドルフの百合』は、旅の途中に嵐に出会ったガドルフ(勅使川原)と白百合(佐東)とのいわば幻想的かつ一方的な恋愛譚だが、朗読が終わったその物語が新たに蘇って、思いもよらない解釈のもとに再展開してゆくことになる。まるで詩のかたちをした文芸批評。『ガドルフの百合』の深淵、賢治の深淵を覗き込む思いである。
私は、勅使川原が荻窪に開いた小劇場アパラタスでほとんど毎月のように新作を上演していることに驚嘆しているが、それはそのつどつねに新たな試みが展開されているからである。身体においてだけではない。
音楽、文学、美術、とりわけ照明すなはち影と空間の研究において凄い。舞台芸術の拡張。世界的に見て最先端を行くと言っていいその成果のすべてが、『ガドルフの百合』に流れ込んでいる。移った影が独自に動き始める。紗幕に映るはずのないものが映る。まるで魔術だ。とりわけ最後の「南の蠍の赤い光」、去って行くべきはずの赤いテールランプが高度を増し爆発して消えたのには呆然とした。勅使川原は照明をオブジェに変えたのである。
「言葉と影の繊細な研究」といっていいアパラタスの克明な上演記録が執筆されることを切に望む。